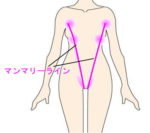サプリメントを飲むタイミングについて
サプリメントは、食後に飲んだらいいのか、食前・食間の空腹時に飲んだらいいのかわからないものがあります。
「毎食後3粒飲んでください。」などと、説明書やパッケージには具体的に書かれていません。
それもそのはずで、サプリメントは健康食品であって医薬品ではありません。
もし、「毎食後3粒飲んでください。」というようなことを書いてしまったら、薬機法(旧薬事法)に触れてしまいます。
薬機法の関係で、次のように書かれているのが代表的です。
「健康食品のため、基本的にはお好きな時間帯にお飲みください。1日6粒を限度に3回程度にわけて水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。」
「食後にお召し上がりいただくことをおすすめします。」
「空腹時の摂取が良いという医師の見解もございます。」
このように、漠然と書かれた内容を飲む側が判断するしかありません。
サプリメントはどのタイミングで飲むと効果的か
漠然と書かれていても、だいたい判断できるものはいいのですが、わからない場合は次のタイミングで飲むと効果的です。
田村忠司『サプリメントの正体』(東洋経済)
ビタミンの摂り方
ビタミンは、油に溶けやすい脂溶性(しようせい)のものと、水に溶けやすい水溶性のものに分けられます。
脂溶性のビタミンは、油分が含まれる食事と一緒に摂ると効果的です。
また、水溶性のビタミンは、摂ると尿や汗に溶けて体外に排出されやすいので、まとめて摂らずにこまめに摂ると効果的です。
| ビタミン名 | 化学名 | |
| 油溶性 | ビタミンA | レチノール |
| ビタミンD | カルシフェロール | |
| ビタミンE | トコフェロール | |
| ビタミンK | フィロキノン | |
| 水溶性 | ビタミンB1 | サイアミン |
| ビタミンB2 | リボフラビン | |
| ビタミンB3 | ナイアシン | |
| ビタミンB5 | パントテン酸 | |
| ビタミンB6 | ビリドキシン | |
| ビタミンB12 | コバラミン | |
| ビタミンC | アスコルビン酸 | |
| ビタミンH | ビオチン | |
| 葉酸(ビタミンM) | プテロイルグルタミン酸 |
空腹時に飲むと効果的な成分もある
<アミノ酸系>
食べ物はまずタンパク質が先に消化・吸収されますので、アミノ酸系の成分を食べ物と一緒に摂ると効率が悪くなります。
アミノ酸系の機能性成分
コラーゲン
タウリン
カルニチン
レクチン
グルタミン酸
カゼイン
カゼインホスホペプチド
ラクトフェリン
<ダイエット系>
飲むと満腹感が得られるサプリメントは、食事をする前に飲みます。
<αリポ酸>
αリポ酸(チオクト酸)には、有害ミネラルや有害重金属を体外に排出する働きが期待されます。
いわゆる「デトックス」効果と呼ばれるものです。
αリポ酸を食事と一緒に摂ると、有用なミネラル分などと反応してしまう可能性があるので、空腹時に摂るのが効果的です。